Palau Horizon紙の2010年8月17日の記事から
この日は、3ヶ月近い学校の学年末休暇が終わって、新しい学年の始まりです。

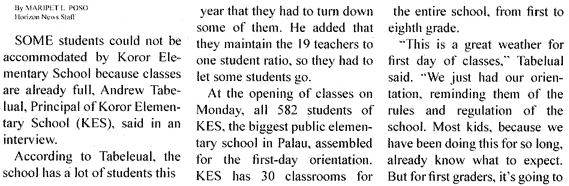
記事を読んでみると、
「コロール小学校では教室が満杯のため、数名の生徒の入学を断った、と校長が語った。 校長によると、一人の先生に19名の生徒という割合を維持するための措置、とのこと。 総勢582名の生徒に30教室・・・・・・」
さらに続けて、
「入学を断られた生徒は他の学校へ行くか、次学期まで待って、もし空きができれば受け入れる。 空席待ちは『早いもの勝ち』だ、我々が決めるものではない。」と。
最後に、校長先生は、教科書の不足もないし、
「・・・・Everything is going well.」 と締めくくっている。
この記事が私たちに示唆するものは何でしょう。
日本ではちょっと考えにくい事態です。
住民登録制度によって、来年何人の1年生が入学するか、ほぼ予測できます。
住民登録制度がまだできていないため、パラオでは来年度の入学児童数をあらかじめ把握することが困難なのかもしれません。(人口の少ない州では可能かもしれませんが、人の出入りが多いコロールではほぼ不可能でしょう)
さらに、住民登録には住所が必要です。 パラオには一軒の家を特定する住所がありません。 市・村とその下位行政区域であるハムレットまでしか把握できません。
これは土地そのものが日本のように土地台帳などの情報として管理されていないことから、当然のことといえるでしょう。 不動産売買など、いろいろ裁判で問題になることがあるようですが、まだ充分に法制化されていないのが現状です。(それでも、パラオ政府によれば、他の大洋州諸国に比べれば、土地制度は整っているほうだ、ということですが・・)
つまるところ、このコロール小の一件は、パラオの行政の根幹にまで行き着いてしまう根深い問題を示唆していた、ということができるでしょう。
こうした、新聞の記事ひとつにも、行間に眼を凝らすと、パラオの持つ問題の根深さ・困難さを感じてしまいます。