2011年1月、パラオの新聞 TIA BELAU紙 に、表題の、ドキッとするようなタイトルが踊っていました。 TIA BELAU紙はときどきこういうセンセーショナルな見出しを載せてくれますが、記事は以下のとおりです。
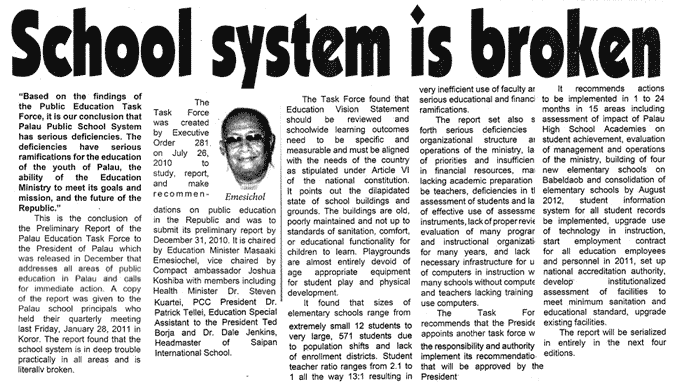
とりあえず、逐語訳してみます。(英語能力不足による誤訳の可能性があります。原文にもあたってみてください。)
———————————————————
公教育特別委員会によれば、パラオの公立学校は深刻な欠陥を抱えている、とのことだ。
この欠陥は、パラオの青年層の教育・目標達成に向けた教育省の能力、しいては共和国の未来にも影響を及ぼす問題だ。
これは公教育特別委員会が大統領に対して12月に提出した予備報告で、パラオの公教育全般に警告すると共に早急な行動を呼びかけている。 報告書は1月28日にコロールでおこなわれた四半期ごとのミーティングで、パラオの各校長にも送られた。報告書によれば、パラオの学校システムは深刻な状態にあり、文字通り「破綻」している、と。
この特別委員会は、2010年6月26日の281号指示により、共和国の公教育について調査・研究し、推奨事項を決定し、2010年12月31日までに予備報告をおこなうよう定められた。 教育大臣・Masaaki Emesiochel を長として、コンパクト大使・Joshua Koshiba を副委員長、厚生大臣・Steven Kuartei, PCC学長・Patrick Tellei, 大統領の教育顧問・Ted Borja, サイパン国際学校・Dale Jenkins で構成されている。
特別委員会は、「Education Vision Statement 教育未来像(?)」は見直されるべきであり、学校での学習成果が測定可能な形で具体化され、憲法6条の定めるところにしたがって国家の要請に沿うものでなければならない、としている。報告書では学校の建物や運動場の荒廃を指摘している。 学校の建物は老朽化し、適切に維持管理されてなく、衛生面や教育機能面で水準以下である。 運動場は、生徒が遊んだり、身体の発達に必要な設備に欠けている。
生徒数は小規模な12名から大規模な571名まであり、教員・生徒数比は、(多いところと少ないところとで)2.1倍の差があり、全体で教員1名あたり生徒13名となり、たいへん非効率的で、教育面・財政面で深刻な結果を引き起こしている。
報告書は、教育省の組織構成や一連の作業の欠陥や、教員になるための専門教育の欠如、生徒評価における欠陥、評価のための道具類を効果的に使えていないこと、多くの計画や教育組織を長年にわたって正しく再評価してこなかったこと、コンピュータがないためにあるいは、コンピュータを使う訓練を教員が受けていないために教育へのコンピュータ活用のためのインフラが不足していること、などを報告している。
特別委員会は、大統領に対して、これらの勧告項目を実施する責任と権限をもつ新たな委員会を立ち上げるよう勧告している。
委員会の勧告事項は今後2年間、15領域にわたって、以下のとおり:
・ Palau High School Academy(?)があたえる生徒の学業への影響評価
・ 教育省の管理運営評価
・ バベルダオブ島の4つの小学校新設と2012年夏までの小学校統合
・ 全ての生徒について生徒情報システムを構築すること
・ 教育における技術の利用の高度化
・ 2011年中に全ての教育の場の被雇用者・教育者との雇用契約をはじめること
・ 国家認定機関の設立
・ 教育・衛生上、最低限の標準を満たすように施設の評価、既存施設の改善
—— 以上です ——–
で、この委員会報告によって、何が始まろうとしているのか、気になります。
日本の国際協力・技術協力のほんの端っこにぶらさがっている私には
上に書かれている内容について評価する材料とてありません。
ただ、やはり「ビジョンが見えないな~」というもどかしさは、こうしたレポートに接するたびに等しく味わいます。
ここに、JOCV(青年海外協力隊)の隊員としてパラオの学校現場で活動していた方のブログ記事を紹介しておきます。 ご本人とは面識もなく、直接了解を得ていませんので引用は差し控えます。
外的アプローチ
ひとつの高い見識を示している、と感じました。