2010年3月頃、新聞をにぎわした事件がありました。
Copelandという特別検事(Special Prosecutor)にまつわる一件で、
米国の法律事務所に数年間勤務していただけのCopeland氏がパラオで特別検事職につき、高給を得、素性が暴かれ、新聞紙上でたたかれ、最終的には国外追放という結果で終わったのですが、国外追放とは言え、きちんと「いただくものはいただいて(年俸65,000ドル+引越し費用10,000ドル)」パラオを離れたようで、その辺りも紙上でたたかれたりしたようです。
今回ここでCopeland氏にご登場いただいたのは、彼のデタラメぶりを再確認するためではなく、彼の身辺調査をおこなった委員会の対応を取り上げてみようというわけです。
ここに新聞(TIA BELAU)のコピーがあります。
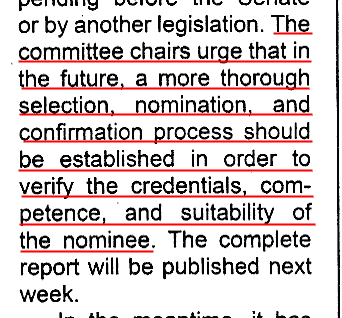
要約すると、
「委員会は、将来、もっと完璧な人選のプロセスが確立されるべきである」と諮問
と・・・
な、なんとおっしゃいますか! 「将来において、・・・確立されるべき・・・」
ということは、今はどうなってるんでしょう? ってことですよね・・・
はっきり言いましょう、「今は(特別検事)人選のプロセスは、できていない」のです
ですが、この一件をもって、「だからパラオはダメなんだ」という決めつけるのは拙速です。 なぜ「人選のプロセスが確立できていない、あるいはできない」のか、を問うべきです。
私の生活メモを覗いてみると、パラオに来て2ヶ月目くらいの頃にこんな記述があります。
「途上国と呼ぶにはどこにも途上国らしさが感じられない。
(途上国にはつきものの、ハエ・カラス・蚊・ネズミ を見かけないし、
途上国へ行けば必ず出会う「物乞い」やスラムも見かけることがない。
スリランカで見た象皮病の悲惨な姿もここでは無縁だ)
途上国一般の、いわゆる『南北格差・南北問題』という切り口では決して
見えてこないパラオのむずかしさをそこには感じとることができる。
それは、
極小行政規模で国家として振る舞い、かつ自立的な国家運営・国家経営を
可能とするために必要なこと・もの、とは何か、という問題、
あるいは、
極小行政規模国家における、自立的行政のための人材養成・技術移転の
問題、という切り口から見えてくる、困難さ、
と言えばいいかもしれない。」
ここで取り上げたCopeland氏の一件も、自立した司法法制・司法人事を確立するには、あまりにも国家経営のプロが足りない、いや、国家経営のプロがいない、パラオの現状を示しています。
それが、上述の発言「・・・将来において・・完璧な人選のプロセスが確立されるべき・・」
につながっているのです。
すこし極端な表現かもしれませんが、
『パラオに必要な国際協力・技術協力は、『国家経営のプロ育成』であって、
専門家やボランティアではなく、
例えば、霞ヶ関の若手中堅官僚を10~20名、集中して1~2年派遣すれば、
パラオは変わるかも知れない』
と真剣に考えたりもします。
国家の仕組み・国家の運営、総じて国家経営という課題を、この極小行政規模国家にまず根付かせることが必要なんじゃないか、そうでなければ個々の技術協力・技術移転の課題はいつまでも『その場しのぎの助っ人』の域を超えることができないかもしれない、と思うこのごろです。
「将来ビジョンが見えないまま、あるいは、あえてビジョンを描こうとせずに、自転車操業を続ける、倒産寸前の零細企業」・・・そんな姿を連想してしまいます。