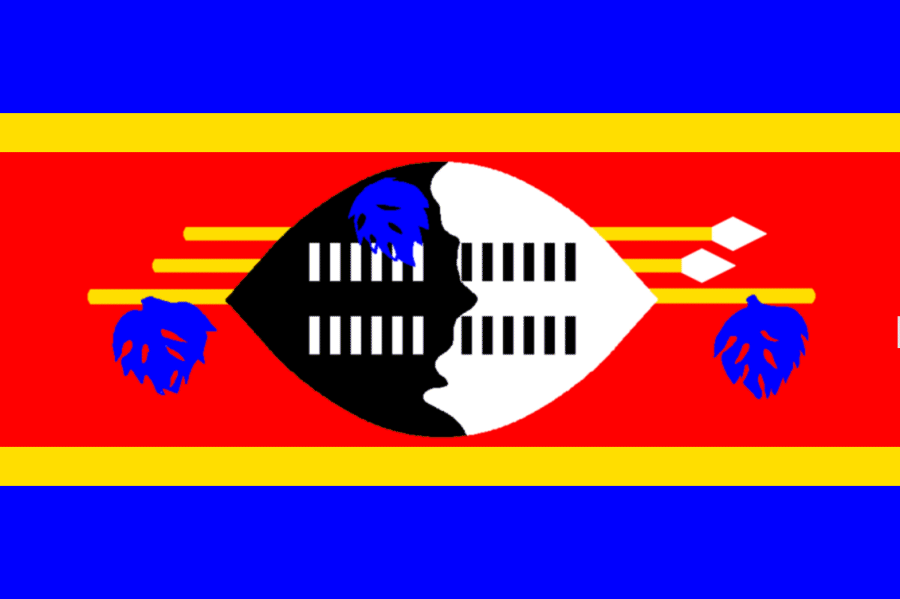2012年11月からSCOT(Swaziland College of Technology)でプログラミングのクラスを受け持つようになって、学生たちの実習の様子を見ているうちに、ある傾向に気がついて少々気になったことがありました。

学生たちにプログラムの作成から実行までの実習課題を与えて、しばらく様子をみていると、何人かの学生が「質問がある」と手を挙げて私をよぶことがあります。 学生のそばに行って、学生が使っているPCのモニタを覗くと、プログラムをコンパイルしたときに発生したコンパイルエラーであったり、実行時のエラーであったり、さまざまですが、共通しているのは、システムが表示しているエラーメッセージを読まないこと。 そして私を呼んで先ず尋ねるのが「どこをどうすればいいのか?」ということ。 コンパイルできないのはなぜか、実行できないのはなぜか、原因を突き止めるのではなく、どうすれば正しくコンパイルできたり、実行できたりするのか、を知ろうとするのです。「知ろうとする」のはまだ良いほうで、多くの場合「操作指示を待つ」という状態です。

なぜそうなんだろう、といろいろ考えてみましたが、すこし大げさに聞こえるかもしれませんが、やはり「小学校以降の教育のあり方」に問題あるのではないだろうか、と思います。
今、週に数回、プログラミングの講座を受け持っている技術短大で、講座を始める前に何度か同僚の先生のレクチャーを見学させていただきました。
感想をひとことで言い表すとすれば、「ほぼ一方通行のレクチャー」ということでしょう。 学生から講師へのアクションは、PCの操作上のトラブル時を除くとほぼ皆無で、学生たちは実に神妙に、約2時間のレクチャーを静聴し続けます。 おそらくこうした傾向は小学校から変わらないのだろうと思います。
かつてパラオでJICAボランティアをやっていたとき、当地の小学校に配属されていた青年海外協力隊員たちから当地の授業の様子を聞いたことがありました。 先生が黒板に問題を板書し、生徒たちがノートに写して解き始め、しばらくして先生が黒板に正解を書く。生徒たちは、その正解を見て「あってた」とか「まちがってた」とか、ノートにチェックする。間違っていれば、正解を書き写す、ただそれだけだった、と。 「どうして間違えたのか」とか「どのようにすれば正しい答えにたどりつけるのか」とか先生からのフォローはまったくなかった、と。
おそらく、スワジランドでも事情は似ていると思われます。
技術短大の学生たちの様子を見ていて、そう思います。「なぜ自分のプログラムはコンパイルエラーになるんだろう?」「このコンパイルエラーの原因は何だろう?」という自問のプロセスがどうも抜け落ちていて、「自分のプログラムソースのどこをどのように修正すればいいか、指示して(=教えて)ほしい」となってしまいます。
これは、知識偏重型の教育に特徴的な傾向なのかもしれない、と想像します。 試験問題をみても、IGCSEの試験問題に典型的に現れているのですが、「知識の有無を試す」問題、「指示通りの操作ができるか否か、を試す問題」がほぼ100%を占めます。「考えて答えをひねり出す」という趣旨の問題は、表計算(Excel)系の問題に若干見ることが出来ましたが、他にはほとんど見当たりません。
おおげさな言い方かもしれませんが、『「教育」という概念に対する捉えかた』というようなレベルの問題なのかもしれないな、と感じます。 教育 = 「知識を与えること」 という捉えかたがベースにあれば、たぶんこうした傾向がでてくるのではないでしょうか?
‘12年9月に実施したICT教員対象のWorkshopで、私は
「先生に教わって得た知識は必ず忘れる。
しかし、自分で調べて得た知識、自分で気づいて得た知識は決して忘れない。
先生の役割は『生徒に知識を与えることではなく、生徒の気づきをサポートすること』」
と先生たちにプレゼンしたのですが、どこまで伝わったか・・・・???
英語力不足による伝達不良のほうが問題だったりして・・・・・
私は「人になにかを教える」、いわゆる先生としては全くのシロウトですが、自分が教わる側、つまり生徒としての経験(もう40年も50年も昔の経験ですが・・・)から、上に述べたようなことを教える立場の人たちに考えてもらいたいと思っています。