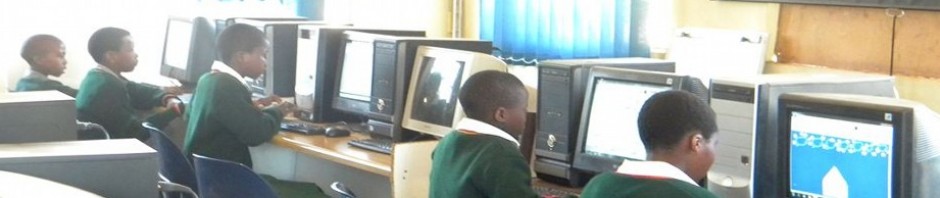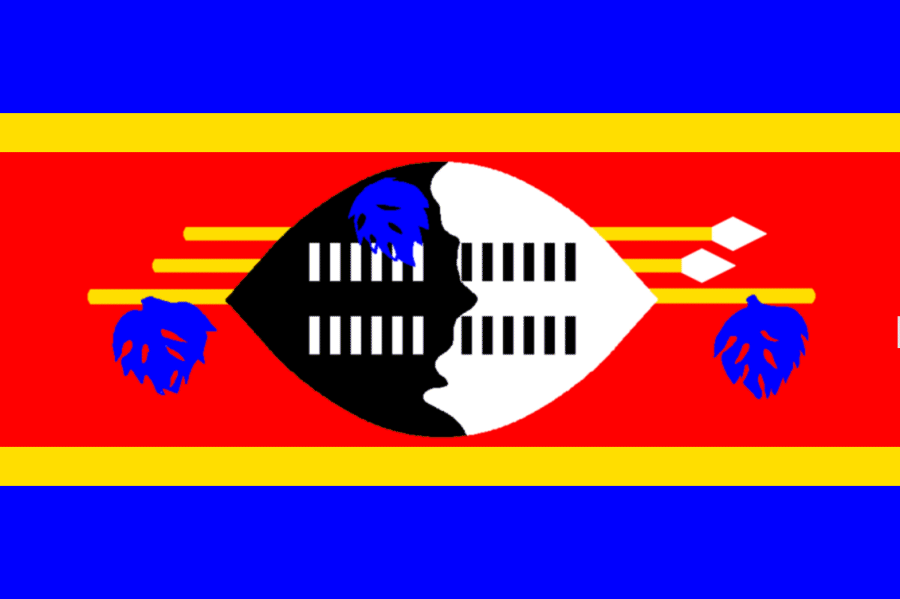かつて、もう30年近く前になりますが、私はJICA(国際協力機構、当時は国際協力事業団といってましたか)の国際協力プログラムのひとつであった青年海外協力隊に参加しました。 当時は任国への派遣の前に3ヶ月間の派遣前訓練がありました。 長野県駒ヶ根市にある訓練所での合宿生活でした。
訓練の中に「任国事情」という科目があって、それぞれ自分の派遣国の国内事情やら文化やら、任国入りの前にできるだけ任国のことをよく知っておこう、という科目です。 私の任国はスリランカで、あの独特なドラヴィダ系文字を勉強したりしたものでした。
3ヶ月の訓練を終え、任国入りし、協力活動らしきことを自分なりにはじめ、現地のスタッフとも仲良くなってお互いにそれぞれの国や文化の情報交換もするようになったある日、ひとりのスタッフが私に尋ねました。
「日本人は、植物でできたマットの上で生活していると聞いたけれど、それはどんな植物?」
『植物でできたマット』というのが『畳』のことだというのは、すぐに気づいたのですが、私は畳がどんな植物でできているか、そのとき知らなかったのですね。 今のように、インターネットなんてない時代、パソコンすらまだ珍しい時代でしたから、すぐに調べることもできず、そのときなんと説明したのか、もう忘れてしまいましたが、冷や汗かいたのはよく覚えています。
それからしばらく経ったある日、お茶の産地で有名なヌワラエリアにスタッフが連れて行ってくれて、茶畑や紅茶工場を案内してくれました。 そしてまた私に尋ねます。
「日本人もお茶(Tea)を飲むそうだけれど、日本のお茶は私たちのTeaと同じ?」
私は、なんとか「緑茶」を説明しましたが、続けて受けた質問でまた冷や汗をかきます。
「じゃあ、そのGreenTeaはどうやって作るの? この工場でTeaを作るのと同じ?」
私は緑茶の生産工程など、その当時知るわけもなく、答えに詰まってまた冷や汗をかきました。
こうした経験でわかったことがひとつだけあります。
「訓練所では『任国事情』で相手の国の文化や生活を一生懸命勉強したつもりだったけれど、もっとだいじなことを私は忘れていたようだ、それは自分の国の文化や生活をもっともっと知って、相手にわかりやすく伝えられるように鍛える訓練だ」ということでした。 これから青年海外協力隊に参加を希望している若い方々がもし読んでいらっしゃるなら、ちょっと頭の片隅にでも置いておかれるといいかもしれません。 訓練所の「任国事情」も半分ほどは「自国事情」とかにして「日本を任国言語で紹介する訓練」にしてもいいかもしれませんね。
相手国の文化や生活については、「私は知らない」といえば、現地の人々は喜んで、それこそ持っている知識を総動員するかのように、教えてくれます。「何も知らない日本人に教えてやらなきゃ」というわけですね。 途上国と呼ばれる国々に住む人々は、ほぼ例外なく、自分たちの生活や文化に誇りを持っています。 彼らにとっては、自分たちの誇りを相手に伝える輝かしい時間、といってもおおげさではないのでしょうね。
30年ほど前の青年海外協力隊の経験のあと、日本で還暦を迎え、またJICAのボランティアプログラムに参加することが決まったとき、先ず最初に私が書店で求めたのは「日本の文化を英語で説明する」という書物でした。 任国については「現地に行けば、現地の人が教えてくれるだろう」ということで、あえて事前学習することなく任国入りしました。
今は「グローバル化」などと言われて、日本人が世界中で活躍する時代です、けれども30年近く前に『畳の材料と緑茶の製法』が私に教えてくれたこと、即ち「日本という国・日本の文化についてきちんと他者に伝えられる自分自身を準備すること」は今でも『グローバル化』の大切な前提だと思います。
余談ですが・・・ヌワラエリアの紅茶工場を見学していたとき、私の同僚(現地スタッフ)が言ってました。
「床にこぼれた紅茶のくずを箒で集めているでしょう、ああして集めた紅茶くずはホコリやゴミを丁寧に取り除いてティーバッグにするんですよ。 だから私たちスリランカ人はティーバッグの紅茶は決して飲まない。」
今では決してそんなことはないと信じてますが、当時はその言を信じて、スリランカではティーバッグを決して買いませんでした・・・余談でした。