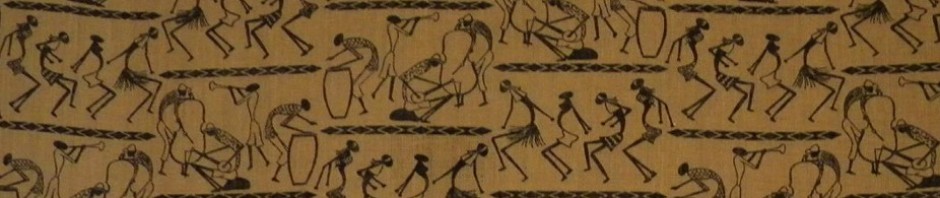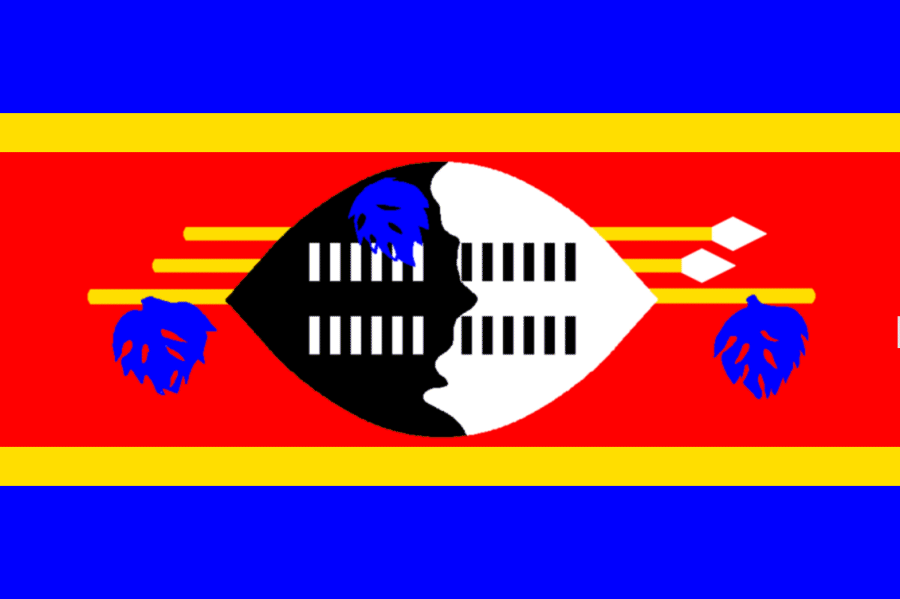スワジランドでJICAボランティアをやってます、と伝えると、「世界の涯(はて)みたいなところですね」とよく言われます。 私自身も、こちらに赴任してしばらくは「世界の涯(はて)まで来てしまった」と独り言をこぼしておりました。
でもよく考えると、スワジランドの人々にとって、「日本こそ世界の涯(はて)」であり、私こそ「世界の涯(はて)から来た人間」だったのですね。 ここでみる世界地図は、私たち日本人が日本で見慣れている世界地図、日本が真ん中にあってアメリカ大陸が東の端、ヨーロッパが西の端、にある世界地図ではなくて、東経(西経)0度を中心に描かれた、おそらく世界標準であろう世界地図です。 その世界地図では、ロンドン標準時と2時間の時差しかないスワジランドも、南に片寄ってはいますが、ほぼ中心に近く描かれていて、日本は、というと、「極東」の名に恥じず、「これ以上東にはなにもない」東の極みに描かれています。
その世界地図で見れば、私が「世界の涯(はて)までやってきた」のか「世界の涯(はて)からやってきた」のか、一目瞭然なんですね。
小学校の地図帳などにも、日本が真ん中にある世界地図といっしょに、世界標準の(=日本が極東である)世界地図を掲載してみてはいかがなものでしょう? 「極東」という言葉の意味も視覚的に理解できていいかもしれません。 幼いうちから、物事を一歩ひいて俯瞰的に見る眼、相対化してみる眼を養えるかもしれません。
もうずいぶん前ですが、オーストラリアを中心に描いた世界地図を見たことがあります。 そこでは南極が上に、北極が下に描かれていました。 さすがにその世界地図を見続けるときに感じる違和感、というか、苛立ちというか、私の頭のなかにある空間認識の融通のなさ、というか、その世界地図を納得することができなかったのですが、その後、月から見た「地球の出」の写真を見たときに、「あ、そうか、丸い地球が昇ってきても、『上に北極、下に南極』であがってくるとはかぎらないのだな」とこのときはなぜかすっきり納得できました。
話がそれてしまいましたが、JICAボランティアをやって良かったな、と思うのは、自分の今いる位置や状況を一歩ひいて客観視しようとする姿勢が身についた、ということ、かもしれません。 そうしないと、途上国では納得いかないことばかりでストレスをためてしまいます。 納得いかない自分の視座(立ち位置)をもう一度リセットしてくれる「もう一人の自分」を感じていること、ですかね。