 スワジランドに来た当初、なにやら正体不明な違和感を感じ続けていました。
スワジランドに来た当初、なにやら正体不明な違和感を感じ続けていました。それは「自分はこの土地にとっては異物である」という感覚に由来するように思えました。
この土地には東洋人は珍しく、日本人は全部でも両手で足りるほどしかいません。
そのような土地で、道行く人はほとんど肌の黒い人であり、すれ違うたびに好奇の眼で見られ、その眼にはたいてい「お前はいったい何者だ」という詰問するような鋭さを感じたものでした。
そのような時期がしばらく続いたあと、自分のなかにあった違和感がなぜか薄れてしまったように感じました。 なぜそう感じたのか今でもわかりませんが、当時ときどき思い出した映画の一場面のことをご紹介しておこうと思います。
 ギリシャの映画監督でテオ・アンゲロプロスという人がいます。 数年前に亡くなりましたが、重厚な作品を多数世に送り出した、私の好きな映画監督です。
ギリシャの映画監督でテオ・アンゲロプロスという人がいます。 数年前に亡くなりましたが、重厚な作品を多数世に送り出した、私の好きな映画監督です。彼の作品に「旅芸人の記録」という、4時間におよぶ作品があります。 もう30年以上前に観た映画なので、記憶がぼんやりしていますが、ギリシャの現代史を描く、彼の「ギリシャ現代史3部作」のひとつ(のはず?)で、1940年代から1950年代はじめのころのギリシャの状況をギリシャ神話のストーリーや人物にかぶせながら描いています。
旅芸人の一座を通してギリシャの40~50年代を描くこの映画の中で、ギリシャ軍事政権に抵抗する左派ゲリラの一人として政権に拘留され、処刑される座長の息子・オレステス(ひょっとすると座長アガメムノンだったか?)が処刑場で自分に銃を向ける兵に向かって、静かにこう語りかけます。
「君はどこからやってきたんだね? 私はイオニアの海からやって来た。」
 昔から、初対面の人に対して、自分自身の出自を語るのが、人と人とのコミュニケーションの「最初の一歩」と言われます。
昔から、初対面の人に対して、自分自身の出自を語るのが、人と人とのコミュニケーションの「最初の一歩」と言われます。例えば、「手前、生国と発しまするは・・・」ではじまる日本のかつての極道の世界の仁義。 これなど典型的な例で、人間のコミュニケーションの根源を捉えた、実にすばらしい文化ですね。
つまり、人と人とのコミュニケーションは、「出自」を問い「出自」を語ることから始まるのですね。
で、スワジランドの街角で「お前は何者だ」という鋭い視線に対して、私は「わたしはここからず~っと遠い『日本』という小さな国からやってきた」と、私の視線でこたえるように、いつのまにかなっていました。
そうして、当初感じていた違和感・異物感と共生できるようになりました。
違和感・異物感がなくなったわけではなく、「共生」できるようになっただけです。「詰問するような鋭さ」を感じなくなっただけです。
そのあたりからスワジランドは私にとって「居心地のいい土地」になりはじめたように思います。

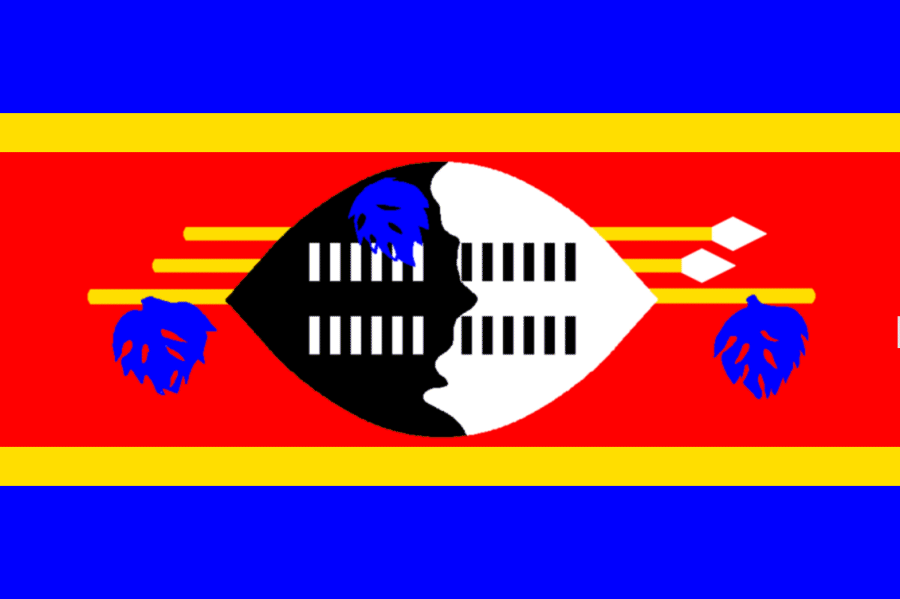
とても楽しく読ませていただきました。
スワジランドについて色々とお聞きしたいことがあるのですが、コメント欄だと個人情報になってしまうので、もし宜しければメールアドレスに、お時間のある時に一言メールしていただけると嬉しいです。
拙いサイトをお訪ねいただき、ありがとうございました。
記載のありましたメールアドレス宛、メールいたしましたので、ご質問等にご利用ください。